小学生のための下水道講座
下水道の歴史(れきし)
日本では昔から農業でし尿(にょう)を肥料(ひりょう)としてつかってきました。しかし明治時代になり、人々が東京などの都市に集まるようになって、し尿がたまってくるようになると、それが原因でコレラなどの伝染病(でんせんびょう)がはやるようになりました。そこで明治14年に横浜(よこはま)ではじめての下水道がつくられました。
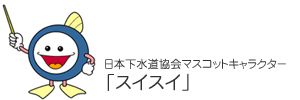
下水道とは?
下水道は、わたしたちがつかってよごれた水を浄化(じょうか)センターにはこんで、きれいにしてから川や海にもどすという大切なしごとをしています。下水道がなければ、よごれたままの水が川や海へながれこんできたなくなり、きれいな水がつかえなくなってしまいます。
下水道がない場合の側溝(そっこう)

きたない水がそのまま川にながれていきます。
いつもしめっていて、蚊(か)やくさいにおいが発生(はっせい)します。
下水道がある場合の側溝(そっこう)

雨以外はながれないので、晴れている日はかわいています。清潔(せいけつ)で、住みよい生活環境(せいかつかんきょう)です。
下水道のしくみ
わたしたちがつかった台所やトイレの水は、道路の下にうまっている下水道管をとおって、浄化センターにはこばれます。そこで微生物(びせいぶつ)がよごれやゴミを食べてくれます。おなかがいっぱいになった微生物は、しずんでしまうので、上にきれいな水がのこります。その水を薬品(やくひん)で消毒(しょうどく)し、さらにきれいにしてから川にながします。
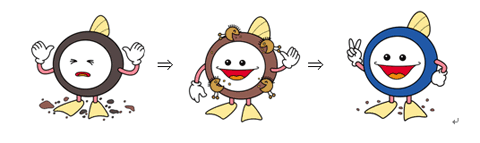
このページに関する問合せ
建設部 下水道課
〒481-8531
愛知県北名古屋市西之保清水田15番地
電話:0568-22-1111
ファクス:0568-25-5533
メール:gesui@city.kitanagoya.lg.jp
